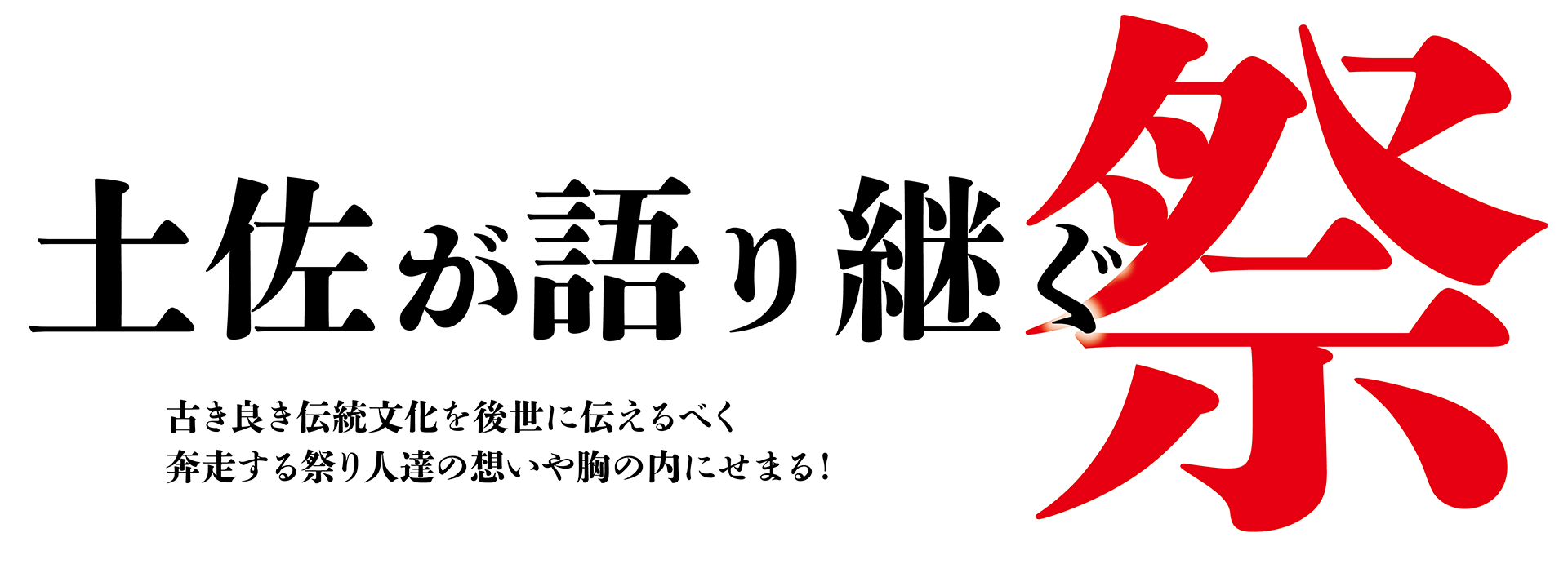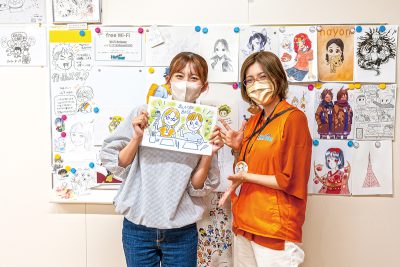空に舞う炎を仰ぎ、健康を祈る
どんど祭り
●安芸郡田野町 二十三士公園 ※令和3年の開催は中止
日本各地で行われる小正月の火祭り「どんど焼き」。悪魔払い、無病息災を祈って、門松やしめ縄などを集めて燃やす日本の伝統的な文化で、どんどさん、さんくろうなどともいう。

年初めに行われる 伝統的文化
毎年1月の第2週目の日曜、奈半利川河川敷にある二十三士公園では、年初め一番の大祭「どんど祭り」が開催される。青竹を骨格として、やぐらを組み、これに火を投じて門松やしめ縄、お札などを焼いていく。前日に準備するやぐらの高さは約7メートルほどで、豪快に燃え上がる炎は、地上から10メートルほど高く上がる時もあるという。中でも一番の見どころは、燃え盛る炎とともに聞こえる、竹が割れる音やはじける音。「パチパチ」と小さな音が聞こえ出したと思いきや、炎の中で竹がはじける「ドーンッ」と迫力のある音が響いたり…、参加者はこの音に耳を傾け、炎に目を向けて、1年の健康と地域の振興を願う。炎が弱まると、長い竹串を使い、お餅を焼き、このお餅を食べることで、1年間、無病息災で過ごすことができるといわれている。
祭りを通じて培う 地域交流
今では、メディアが取材に訪れるほど大規模な祭りとなった「どんど祭り」だが、そのルーツは一人の教職員の「子どもや地域住民が楽しめる、地域に根差した行事をしたい」という思いだった。安芸郡東洋町に赴任し、どんど焼きの文化を知った元校長先生が田野町上地・日野地区に持ち帰ったことがきっかけとなり、昭和59年に第1回目が開催。その後、2回・3回と年数を重ねるごとに、評判を聞きつけた住民が町内外から訪れるように。代々、どんど祭りの主催を務める上地・日野地区長の桑名さんは、今後の展望をこう語る。「どんど祭りは今まで一度も中止になったことがなく、地域住民の協力のおかげで成り立ってきました。高齢化に伴い、大変な事もありますが、健康と団結力を願って長く続けていきたい。今後も、田野町の伝統的文化として残していきたいです」。ルーツとなった思いを受け継ぎ、祭りが続くことを願うばかりだ。
真冬に海水をかぶり防火祈願
水浴びせ
●幡多郡大月町古満目地区 ※令和3年の開催は中止
大月町の小さな漁師町で、毎年正月に開催される「水浴びせ」。若者に冷たい海水を浴びせることで、地域の防火と厄落としを祈る。水をかぶって凍える若者の顔には笑顔がこぼれる。

江戸時代から続く 防火祈願の奇祭
大月町古満目地区の伝統神事「水浴びせ」の起源は江戸時代にさかのぼる。漁師町である古満目は、身を寄せ合うように集落の家々が近距離で建ち並び、冬になると西からの冷たい強風にさらされる。そんな小さな集落に、大火が起きたのは寛文2年(1662年)のこと。1軒の民家で起きた火事が、瞬く間に家々に燃え広がり、地区のほとんどを焼失させるという大惨事となった。以来、「そんな大火事がもう二度と起こらないように」と一心に願い、防火祈願の祭事が始まった。それが、今日まで受け継がれる「水浴びせ」の由来だ。 1月2日に開催される「水浴びせ」奉納行事は、「奇祭」ともいわれるほど独特。凍るように寒い冬の日に、祭りを取り仕切る役員たちが、ほとんど半裸に近い浴衣姿の若者に、バケツいっぱいの冷たい海水を頭から浴びせ掛ける。会場にはたくさんの地域住民やカメラマンが集まり、若者らに激励を送る。何度も水をかぶり、ぶるぶると凍えながらも、若者たちは笑顔を絶やすことはない。こうして毎年、古満目の防火と、かぶり手である若者たちの厄落としが祈願される。
温かいお風呂をためて待っている

「多い時期では20人以上の若者が参加していたが、今ではもう、その半分ほどになっている」と話すのは、古満目地区長の中野清光さん。祭りの役員を22年もの間務め、自身も中学生の頃に水をかぶった経験者。「伝統だから絶やすことはできないですね。毎年、必ず訪れる若者がいるから、彼らのためにもやめたくない」。近年では、水浴びせの話題を聞き、「物は試し」と興味本位で参加する若者も少なくないという。そんな若者の参加者を中野さんは喜んで迎える。「温かいお風呂をためてまっていますよ」。