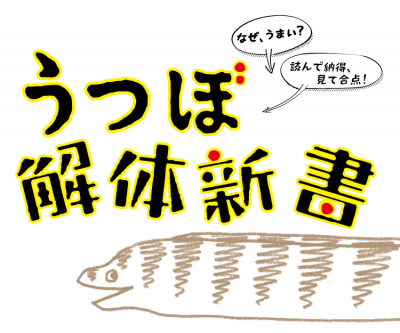かつては「食の拠点」として地域の中で存在感を示したスーパーマーケット。
その原点に遡り、現在の取り組みに触れると「地域に伝わる文化と人々の暮らしとを支える拠点」として変化する姿が見えてきた。
スーパーマーケットが日本に初めて上陸したのは1953年。その5年後、高知県にも、帯屋町2丁目に高知スーパーマーケットが登場した。これを契機に、5年間で46店が開店し、スーパー先進県と呼ばれた時代もあった。サニーマートやサンシャインチェーン、サンプラザ、ナンコクスーパー、エースワンなど県内各地に数々の地元資本のスーパーマーケットが生まれた。しかし、平成に入り県外資本のチェーン店が続々と進出。時の流れとともに閉店した店も多い。
かつては最先端の流行の品を取り入れ、価格競争を繰り広げてきたスーパーマーケット。コンビニやドラッグストアが品ぞろえやサービスを高めて進出する今、スーパーマーケットは「個性」に生き残りをかけている。その個性を「地域密着」に求めるスーパーマーケットを追った。
町から一歩も外に出ない。
地域限定商品で観光客を呼び寄せる。
土佐山田ショッピングセンター[香美市土佐山田町]

土佐山田ショッピングセンターのルーツは、米や食料品を売る石川盛喜商店。旧商店街に押し麦工場を操業するなど手広く経営をしていた。高知スーパーマーケットが土佐山田に進出したことを契機に、「このまま米屋をしていてもいけない」と町内の仲間に出資を募り、翌年の1963年1月にスーパーマーケット・主婦の店山田西店を立ち上げた。バブル崩壊後の1994年にはディスカウント店へと舵を切り、安ければどこからでも商品を仕入れるようになった。
食の学びを応援する
1994年に高知に戻り家業を継いだ石川靖さん(46)。自ら仕入れた商品がよく売れたり、「おいしかった」と言ってもらえたり、充実した日々を送っていた。
ある時、営業部長が地元のコスモス祭りの会場に通りかかったところ、主催者の酪農家に声をかけられた。「おまんくは、ひまわり牛乳を置いてないろう」。当時店長だった石川さんはその話を聞いて、「確かに自分も〝ひまわり〟で育った」と納得。試しに安い県外産の牛乳が並ぶ売り場に、20〜30円高い地元の牛乳を並べてみた。不安もあったが、ダントツの売り上げになった。「高くても地元産の商品は必要とされている」。この経験がディスカウント店から転換するきっかけとなった。
もう一つ、大きな出来事があった。次男が生まれた頃、妻が自分の店で買い物をしなくなった。理由は子どものアレルギー。子どもの健康を案じて、「おいしい」食べ物から、「無添加」の品を探し求めるようになり、妻が集めたカタログには天然醸造の醤油や味噌が並んでいた。「こんな世界があったのか!」。以来、これまで通りの商品の隣に無添加の商品を並べ、その特徴を記したPOPを作り、お客さんが選べる売り場にした。
さらに考えを進める。高知は土佐節発祥の地なのに、店で売れるのは粉末出汁。若者は出汁の取り方を知らないし、料理が家庭で継承されにくくなっている。「だったら、店でやろう」。コンビニや飲食店ではできなくてスーパーマーケットができること、それは「料理を作る人を応援すること」だと辿りついた。2013年には地元の高校と協働した高校生レストランを開催。2015年には店の隣に料理教室専用ルームを開設し、味噌作りや玄米菜食の料理教室などが好評を博している。

観光に来た人が立ち寄る
地元の農家が育てた米や野菜、手づくりの豆腐やお弁当、お惣菜などを販売する産直市「山田のかかし市」。10年ほど前に店内に作ってから、次第に面積を増やしている。「世界中からより良いものを集め、より安く売ることよりも、地域の農作物をちゃんと売りたい」。優先順位は、地元産、県産、四国産、国産という、ローカルかつディープな地産地消。
その素材はお惣菜工場にも運ばれ、添加物をできるだけ使わず調理されるようになった。そうした発想を基にして創作した、地元の雪ケ峰牧場のジャージー牛乳と地元の農家が育てた万次郎かぼちゃを使ったプリンが2013年、全国の品評会で最優秀賞を受賞。この道で間違いない、と少し自信が持てた。「地域には地域ならではの素材があるし、どこにもないオリジナル商品を作ることができる。そうしたら店の品ぞろえががらっと変わって一気に差別化できる。これまで地域にとどまることは弱みだったが、逆に個性になる」。地域の個性を出した商品を持つことで、「道の駅」のように、地元の人だけでなく観光に来た人を呼び込むことができると期待する。
昨年は高知大生、今年は県立大生、2年続いて新卒採用に踏み切った。今春入社予定の吉村沙貴さん(22)は土佐山田町で育ち、大学では地域づくりの活動で多くの経験を積んできた。「地元のいいもの、おいしいものを集めてくる、地域バイヤーを目指します」。土佐山田に新しい風が起きている。
トレンドと地域の状況を睨み
新サービスを展開する。
株式会社くりはら[宿毛市]

豊かな漁場を臨み、古くから海運業が発達した高知の西の玄関口・宿毛市。多くの政治家を輩出し、さまざまな商業が栄えていた。1952年に創業した呉服店くりはらは、1970年頃に「和服から洋服へ!」と全国チェーン「ニチイ」に加盟し、衣料品店をオープンした。ニチイが食料品を扱う「マイカル」事業を始めると、「衣料だけでなく食料でも宿毛を支えたい」と決意。長田町の土地を3年がかりで交渉して購入し、1980年、サングリーンクリハラを出店した。
多角経営で接点を増やす
平成に入り、くりはらは電器店デオデオ(現・エディオン)、ホームセンター・ダイキのフランチャイズ権を獲得し、相次いで出店。外食のモスバーガーやコンビニのサンクス、さらにフィットネスとして高知に進出しはじめたカーブスも出店し、100人以上が働く企業になった。全国的に流行する店が出店しにくい地理的条件を逆手にとり、蓄えてきた資本力を活かしハードルの高いビジネスにも積極的に参入。多業種多業態の展開をしてきた。
その背景には宿毛の地域性がある。坂井義延(67)社長は、「高速が延伸する前は宿毛から高知まで半日かかった。買い物に行くには松山の方が近く、高知の企業は参入してこないし、地域の人の期待に応える形で多角経営できた」。
衣食住を担う宿毛の企業として、もっと地域の人の声を経営に反映させようと、2015年、地域密着プロジェクトを立ち上げた。くりはらで働く社員やパートの8割が女性、なおかつ、ほとんどが宿毛市に暮らし、お客さんとは顔見知り。各部門から1人2人が集まり、それぞれ企画を立てた。田植えから草刈り、稲刈り、店頭での販売まで行う「親子で米作り」、クリスマスには市民合唱団のコンサートを行うなど、市民との接点を大切にした取り組みをしている。
人を育て、生かす
 鮮魚係を長く務めている三松義高専務(67)。宿毛や深浦の市場で培った目利き力は評判となり、東京の料理店からも注文の電話がかかってくる。
鮮魚係を長く務めている三松義高専務(67)。宿毛や深浦の市場で培った目利き力は評判となり、東京の料理店からも注文の電話がかかってくる。
ある日、市長が相談にやってきた。「これで宿毛を代表する特産品を!」。手には広島県田熊で発見されたスダチの一種の「直七」。酸味がおだやかで、香りもまろやかなのが特徴だ。40年前に県内数か所で栽培を始めたものの、そのままでの販売がとん挫し、もはや幻の柑橘となっていた。「子どもの頃から慣れ親しんだ直七。キビナゴの刺身にもイワシの丸干しにもよく合う。これならいける!」。宿毛の農家の庭先にかろうじて残っていた直七から試作品を作り始めた。
三松さんは、かつて大阪のプラスチック加工メーカーで勤めていた頃、全国に流通するお菓子のパッケージを手掛けた経験があり、物流のイロハは叩き込まれていた。宿毛を代表する商品にするには大手メーカーとの契約が鍵になると考え、徹底した衛生管理ができる加工場を建てた。
そして、ユズとは違う路線を模索し、照準を「中華」へ定めた。中華料理の551蓬莱なんば店で直七の果汁を使ったポン酢の試食をしたところ大絶賛。2015年、カゴメ野菜生活の限定フレーバーとしても採用された。現在、直七商品はポン酢しょうゆ、ドレッシング、コンフィチュール、リキュール、あめ、シャーベットの6種があり、売り上げは1億4000万円。さらに40億円を目指す。そうなれば宿毛を支える産業になる、と意気込む。

スーパーからメーカーへ。
豊かな山の幸を商品化し県外に売り込む。
末広ショッピングセンター[土佐町]

早明浦ダム建設計画が始まった1958年、本山町汗見川で農業をしていた山下末広さんは「これからは商売や!」と、ダムのすぐ下の土佐町中島に米を売る「末広商店」を開店した。まだ自家用車が普及していない時代にアメリカに視察に行き、「これからはモータリゼーションがくる」と確信。新しくできるバイパスの隣に駐車スペースを構えた土地に店を移したのは1966年のことだった。自動車の普及と共にお客さんが増え、1970年、ショッピングセンターに。二代目の山下修さん(67)は他地域にも展開しようとするが叶わず、「外に出られないなら、この地域の一番店に」と店舗を350平米に広げ、店の隣に調理場を建て、その上に結婚式場・宴会場もオープンした。
メーカーになりネット販売する
第二次ベビーブームの1972年頃を境に、土佐町の高齢化と人口減のスピードは加速し、商圏は縮小する一方。このままでは大型化したスーパーマーケットは続けられない。「生き残るには、地域性を反映した商品で地域の外にお客さんを作るしかない!」。
1997年頃から地元出身者や高知県人会から名簿を集め、娘が入社した1999年に通販システムを取り入れ、カタログ販売を始めた。仕入れ品を売るだけでは利益が出にくく、「まんじゅうを作ったら蔵が建つかも!」と一台800万円の包餡機を購入。昔ながらの酒粕まんじゅうや、大豊町に伝わる日本で唯一の二段発酵茶・碁石茶を使った大福など、自社製造のアイテムを増やしていった。お菓子以外のユニークな商品を探したところ、自社の宴会場で好評の土佐ジローのすき焼きのたれが浮上。瓶詰にして販売すると、台湾で人気に火がついた。
現在、総売上は約15億円。うちカタログによるネット販売は約4000万円ほど。新社長に就任した谷脇敦さん(41)は、「2040年には嶺北の人口は7000人を切る予想が出ています。オリジナル商品を生み出すメーカーになれば、外で新しい市場を広げられるはず」と、売上倍増を目指す。

 わずか1軒でも末端まで届ける
わずか1軒でも末端まで届ける
食料品や日用品を取り扱う山間部の商店が閉店するのを見かねて、1997年、お届けサービス「フレッシュ便」を開始した。電話で注文を受け、店から商品を集めて届ける。買い物に行く時間がない人や高齢者から評判が広がり、「○○持ってきてや〜」「明日は刺身が食べたい」といった個々の声に応えてきた。
しかし次第に、「耳が遠くなって電話もようせん」「移動販売車が停まるところまでよう歩いていかん」という独居の高齢者が増え、2015年、玄関先まで移動販売車が訪れる「とくし丸」に転換。パートナーである個人事業主に商品を提供し、担当エリアを回ってもらう仕組みが特徴だ。地域にチラシを配ったところ、フレッシュ便の時よりも多い120軒から要望があった。販売パートナーの和田さんは、週に2回、軽トラックに1000点を越える商品を積んで、ようやく乗り入れできる山道もいとわず走って各家を回る。「こんにちは、なにか必要なものはありませんか」と、まるでサザエさんの三河屋さんばりにかけ声が山に響く。
現在は、土佐町、大川村、本山町を3コースに分け1日約30軒を訪問する。今春からは大豊町のコースも増える予定だ。1日の売り上げは8〜9万円で、全国平均を上回る。谷脇社長は「困った声に応えたい気持ちで始めましたが、やっぱりニーズがあったということ」と手応えを感じている。利益が出にくい困難な地で、「暮らし密着」の取り組みが進んでいる。
元は小さな商店からスタートし、地域の歴史や伝統、人々の暮らしやつながりを大切にしながら、変化してきた高知のスーパーマーケット。高齢化、人口減、若者の流出という時の流れの中で、お祭りなど楽しみだった地域の行事は継続も危うくなり、人々の暮らしが支えにくくなっている。「地域愛」に目覚め、具現化しようと挑戦する〝地スーパー〟には、高知の未来の暮らしが映っている。