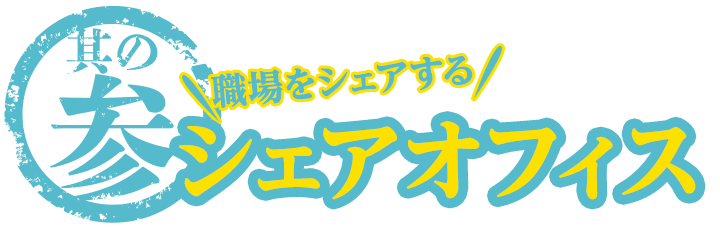空間をシェアし、技をシェアし、想いをシェアする… ここは互いを高め合う新たなコミュニティ。
シェアすることを重んじた土佐人の気質が今の若者に繋がる。
シェアオフィスが昔と今を繋ぐ
一つの建物を複数の団体や企業が間借りするシェアオフィスが、先人と若者、昔と今を繋ぐ接点として、田舎町に新たな人の流れを生んでいる。四万十町の旧広井小学校をシェアする「シェアオフィス161」はまさにそのモデルケースだ。管理人を務める「一般社団法人 いなかパイプ」が中心となって、シェアオフィスの新たな価値を創造。若者向けには、地域のおんちゃん・おばちゃんを先生に、野菜作りやわらじ作り、い草バッグ作りなどの教室を企画。逆に地域のおんちゃん・おばちゃん向けには、若者が先生となってパソコン教室を開催するなど、互いのニーズをマッチング。それぞれが培ってきた技術をシェアすることで、普段は接点を持つ機会のない世代間に交流が生まれている。
シェア仲間は海外からも…
もちろん、ここを利用するのは地域の人たちだけではない。例えば、ロンドン在住の日本人が1週間オフィスをレンタルして、仕事の傍ら自然を散策したり、地域の人と触れ合ったりと、悠々自適にときを過ごしていくケースもあれば、都会から若者を招いた「田舎体験」が行なわれることもある。ここは一見、田舎の閉鎖的な場所に思われがちだが、「田舎とは思えないくらい刺激が多い、常に情報や人が行き交っている」と、4年ほど前から入居する「株式会社 四万十ドラマ」のスタッフも語る。同社の取引先となるのは、お茶組合や栗農家さんなど地域の業者さん。打ち合わせの流れで、シェアオフィスの仲間を巻き込み校庭BBQ… なんて光景も珍しくない。そんな他愛のないコミュニケーションの中にこそ、ヒントやアイディアがあるのだと言う。
カフェもシェアする!
シェアオフィスの一画には「パイプカフェ」という名のカフェスペースまで存在する。ここもまた、好きなときに誰でも使えるシェア空間。この日は月2度ほど利用しているというママ達が集っていた。子どもを遊ばせながら~、手仕事をしながら~、相談しながら~、と何かをしながら時間と空間をシェアするのがママ達のモットー。正午になると、ランチのおもてなしまで。そこには、待ってましたとばかり、全オフィスからランチを求めて入居者が訪れるという「学校だけに給食!?」を思わすユニークな光景が広がっていた。
土佐の伝統に通じるシェア文化
オフィスをシェアすることで、一企業では生まれてこなかった新たな価値がときとして生まれることがある。触れ合い、学び合い、語らい、シェアすることで生まれる可能性は無限大。そんなシェアオフィスの営みは、人と人の交流を古くから重んじる土佐人の気質を受け継いでいるかのようだ。
シェアショップ

築70年の廃校舎が生まれ変わり発見に満ちたシェアショップに!
高知市の菜園場商店街にある「corens」は、かつて洋裁学校として70年もの時を刻んだ校舎がリノベーションされ、多様なお店が入店する複合施設。カフェをはじめ、雑貨・美容・整体・ヨガなどのサロンから、デザイン事務所、雑貨作家のアトリエまで14の個性がひとつの建物をシェアしている。「ここじゃなかったらうちには来そうにないようなお客さんもよく来ますね」とある店主が語る通り、興味を持って訪れた人の多くは、次のお店、また次のお店へと巡り歩く。客にとっても、店にとっても、新しい発見や出会いの連続。こんなところにも、シェア文化を見つけた。
 技をシェアした土佐酒文化
技をシェアした土佐酒文化
伝統を守るには「攻め」が最大の武器。1つの蔵元ではなし得ないレベルに達するために18の蔵元が行ってきたこと。
技術をシェアする土佐酒文化は、杯を酌み交わし杯をシェアすることで生まれた。

古くは江戸時代より土佐酒文化が栄えた高知県には、現在18の蔵元が存在している。酒造りの時期になると、高知県工業技術センターの職員が全ての蔵元を巡回し、醸造データを収集。「新しい酵母が何日目にどう変化したか」「醪(もろみ)の経過はどうか」など様々な情報が数値化される。そして、そのデータが全蔵元にフィードバックされるというから驚きだ。苦労して手に入れた酒造りの技を公開するなんてことは他県ではあり得ない。では、なぜ高知ではシェアするのか? 「18蔵元みんなでレベルを上げていこう」という志が合致したためだ。「守るべき伝統ももちろんあるが、時代に合わない酒造りをしても意味がない。しかし使ったことのない酵母に挑戦するのはどの蔵元も抵抗がある。そこで経験のある蔵元が技をシェアすることである程度知識を持って始めることができる」と酒造組合理事長の竹村さん。ゼロベースからスタートする他県の酒造りに、土佐酒が圧倒的な差を付ける所以はこれだ。秘密にしたい技をシェアすることを受け入れられたのは、杯をシェアし杯を酌み交わし、なんでもシェアする文化が根付いている高知だからこそ。これぞ、後世に受け継ぎたい土佐の精神だ。