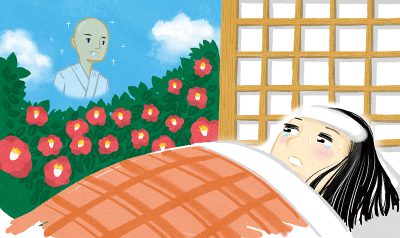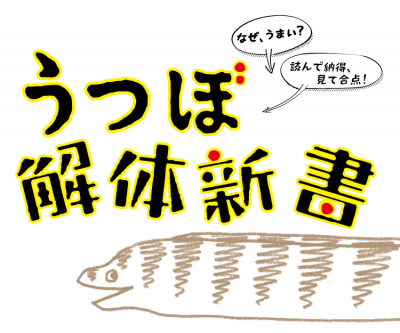端午の節句にこいのぼりと並んで、五月晴れの空にはためくフラフ。 土佐伝統文化として、代々、受け継がれたフラフ作りを行う職人を訪ねた。
空になびく
大きなフラフを未来に
【ハチロー染工場】
とりわけフラフの文化が根強い、香長平野。物部川の豊かな水を利用できたため、かつては染物屋もたくさんあり、土佐湾から吹いてくる強い風を受けて大空でダイナミックにはためくよう、巨大なフラフが作られてきた。
ハチロー染工場の三代目・三谷隆博さんにもまた、祖父から大きなフラフを贈ってもらった思い出がある。「長辺で7mはありましたね。
他にも近所の家や親戚筋から、何枚もフラフをもらって。この辺りでは、そんなふうにフラフを贈り合っていたものです。
節句の時季は、そこかしこでフラフがなびいていましたね」。ハチロー染工場の特徴は、極彩色の色使い。赤の隣には黒など、鮮やかでメリハリがある原色の世界を描き、そこで桃太郎や金太郎といった豪快なモチーフが踊る。
「父からは、こじんまりした染めにならないよう、大胆に、と学びました。フラフは元気を与えてくれます。フラフを見上げて、上を向いていきましょう」と話してくれた。
父の人柄のように人を明るくする作品を
【吉川染物店】
「フラフ作りが忙しくて、正直自分の節句の思い出がないんです。まともに祝ってもらえてなかったかもしれない」と苦笑するのは吉川毅さん。
「吉川染物店」の五代目として生まれ、若干10歳の頃からフラフ作りの手伝いを始めた。
「学校から帰って夜中まで手伝ってお小遣いが500円。割りに合わんな」と子ども心に感じながらも、「息子としてではなく一人前の男として扱われたことがうれしかった」と当時を振り返る。「父は放任主義でフラフ作りも特に習ったことはない。
けれど、職人の心構えをはじめ学ぶことは多かった」。
そんな父の「土佐の伝統文化を残したい」という思いを受け継いで約30年、染色技術や力強い墨線を用いる画風を踏襲しつつも、柔軟に新しいことを取り入れながら活動してきた。
当面の目標は「人を明るくするような作品を生む」こと。「コロナ禍でつらい日々を送る中、見て和んでもらえるようなものを作りたい。明るい性格でみんなに好かれた父のような、そんな作品を」。
技と共に受け継がれる気立て
【佐竹染工場】
「赤ん坊の頃、祖父が張り切って僕のフラフを作ってくれていたと聞きました。
写真を見れば、染色もモチーフも商品で作っている物とは、まるで違いましたね。」そう語るのは、佐竹染工場の八代目、佐竹将太郎さん。
伝承によれば、佐竹家は室町時代に中村(現在の四万十市)を開いた一条氏に付き従い、京都からやってきた紺屋の家筋。
現在は、大漁旗を中心に手掛ける地元唯一の染物屋だ。そのフラフの特徴は、単色に塗り上げられた目の覚めるような背景色。
それも全てがむらなく均一に染められており、とても美しい。「この技術だけは、親父から口酸っぱく教えられました」と話す将太郎さんも、「そんな親父も僕の息子に張り切ってフラフを作ってくれた。
まだ名前も決まっていなかったのに」と笑う。「この先、僕も孫ができたら、きっと張り切ってフラフを作りますね」。フラフ職人もまた、孫のために張り切るおじいちゃんになる。伝統の技と一緒に、気立ても受け継がれていく。