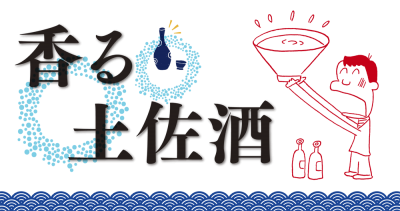ブランド化を目指し土佐茶農家大奮闘! これからは、はちきん女子の腕の魅せどころ
高知県の地場産業の一つとして、古くより山間地の暮らしを支えてきたお茶産業。仁淀川水系や四万十水系の昼夜の寒暖差が育む高知のお茶は、全国的にも非常に評価が高く、静岡県産の高級ブランド茶にインパクトを加えるブレンド用として重宝されてきた。しかし、その価値を知るのは茶業者のみ。一般的に日の目を見ることはなかった。しかし、日陰の存在として位置づけられていた土佐茶が、近年、脇役ではなく主役としてぐいぐい認知度を伸ばしてきている。

混ぜられるお茶からの脱却を目指し、高知のお茶農家がこぞって商品化に乗り出したのは、今から20年程前。その背景には、お茶農家の存続を危ぶむ深刻な問題があった。若い世代を中心に日本人の食卓から遠ざかってきたお茶市場に、ペットボトルの緑茶飲料が登場。2000年代には市場価格が暴落し、30年間で県内の栽培面積は1000haから200haまで減少。ブレンド用の荒茶として出荷していた農家の多くはお茶栽培から撤退を余儀なくされた。そんな中、生き残りをかけ、直販に乗り出すお茶農家が浮上。それをバックアップすべく、高知県は土佐茶販売対策協議会を設立した。テレビCMや量販店、イベント出店など、ブランディングのためのPR活動を積極化。高知市中心街には、PR拠点として「土佐茶カフェ」を整備するなど、土佐茶が県民にとって身近な存在となってきた。

「土佐茶カフェ」に土佐茶アドバイザーとして着任したのは、静岡茶の製造会社に勤めていた中野京子さん。偶然にもUターンのタイミングで縁あって抜擢。「オープン当初はコーヒーが欲しいというお客さんが多く、コーヒーを提供しようか迷った時期もありましたが、それは止めようと決意したんです」と当時を振り返る。高知の喫茶店でお茶と言えば、サービスの一環として食後に出されるもの。それにお金を払う習慣がない県民にお茶をオーダーしてもらうため、試行錯誤の繰り返し。ようやく、「スイーツと一緒に土佐茶を味わってもらう」今のスタイルにたどり着いた。そんな一方で、日本茶インストラクターの肩書きを持つ柿谷奈穂子さんが高知に縁あってIターン。JA津野山にて、土佐茶の商品開発に携わった後、独立。テレビ出演や、お茶イベント「ツノチャ・マルシェ」の実行委員長を務めるなど、土佐茶PRにさらに拍車がかかる。そんな想いに引き寄せられるように、土佐茶に魅せられた女子達が徐々に集結。現在では、霧山茶業組合の中山美佳さんを筆頭に「土佐茶普及促進女性会議」、通称・土佐茶女子会なる組織まで立ち上がり、女性ならではのセンスを武器に、じわじわ土佐茶ファンを増やしている。
土佐茶サポーター養成講座
前半は、日本茶インストラクター・柿谷奈穂子さんより土佐茶の講義。続いて、霧山茶業組合さんのワークショップで、温度による香り・味わいの違いや、ブレンドによる味のバリエーションを楽しんだ。この日の茶葉は、番茶、紅茶、くき茶、かぶせ茶、ほうじ茶、玄米茶の6種類。それに、生姜、文旦、柚子ピール、黒糖、あぶり玄米、ミント、梅シロップなど、フレーバーをブレンドしオリジナルティーを満喫♪
地域の人達の声をたよりに… 主婦のアイディアが生んだ普段使いの土佐茶

高知県の茶農家の先陣をきり、主婦目線で商品化に乗り出したのは、「土佐茶普及促進女性会議」の発起人でもある「霧山茶業組合」の中山美佳さんと矢野靖さん。同組合の理事を務める夫らに、「これからの時代、茶農家も生産者の顔が見える商品が必要だ」と背中を押され、1995年に商品開発に着手。「生活の中でお茶を飲むのが一番多いのはご飯のとき。100g・1000円以上の上質茶より、ご飯のときには手頃に飲める番茶がえい」と普段使いできる100g・200〜300円のお茶を商品化。地域のイベントや子どもの学校行事でお茶を振る舞い、触れ合うお客さんの声に答えるように商品を増やしていった。
「地域の人に愛されるお茶」を目指し、シーンやターゲットに応じて商品を構成。その中でも、「子どもは猫舌やき、熱いお茶より冷えたお茶が飲みたいはず」との想いで商品化した「水出し玄米茶」が今だ一番人気を誇る。畑仕事に、商品化に、イベント出店に、家事に、子育てにと、忙しい主婦が生んだ忙しい主婦のための土佐茶は、県内の量販店に流通するほど浸透。順調に商品化が進む中、2人が次に目指すは「茶畑ワークショップの展開」。女性ならではのアイディアは溢れるばかりだ。