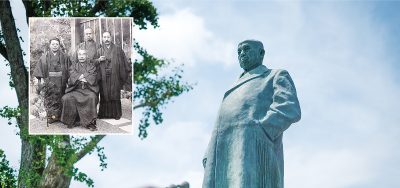高知の喫茶は、自由だ!
アサヒルバン喫茶
〜朝昼晩、それぞれの喫茶に高知が息づく〜
街が、人が、高知の自由な喫茶文化を育ててきた
人口千人あたりの喫茶店の数は、実は高知県が日本一。過去には、そんな調査結果(※)が出たこともあるほど、高知は、喫茶文化が根付いた場所。喫茶店の看板は、市街地や港町、山あいの集落などあらゆる場所に立っており、「ゆっくりしていかんかえ」と目にした人を誘っているようだ。
ではなぜ高知では喫茶文化が盛んなのだろう? 歴史をひも解いてみると、日本各地で喫茶店が増え始めたのは、戦後の昭和20~30年代のこと。開業のハードルが比較的低かった喫茶店は、当時の人々にとって貴重な選択肢だったのだろう。
高知でも、夫婦や家族で営む個人店が次々と誕生し、中でも女性店主が一人で切り盛りする姿は、高知ならではの風景であった。新しいことを始める人を受け入れる県民性も追い風となり、商店街や駅前、町のあちこちに喫茶店が広がっていったのだ。
経済が発展していった昭和40年頃には、映画館の急増と結び付き、上映後に談笑するなど、喫茶店は「おしゃべり好き」といわれる高知人の憩いの場に。また、芸術家が集うサロンのような喫茶店も生まれたという。
ある喫茶店のマスターは、「昔の喫茶店はサラリーマンのおさぼりスポット。高知は女の人がよう働くき、男の人がさぼるがよ(笑)」と半ば冗談のように当時を振り返る。
自由気ままで、熱っぽく、話すことが大好き。そんな高知の人たちにとって喫茶という空間は、気軽な歓談に、熱い文化議論に、はたまた羽を伸ばすのに。自分たちが居心地の良い過ごし方を満喫するのにぴったりの場所だったのかもしれない。高知県民にとって喫茶店は、コーヒーを飲むだけでなく、人と人をつなぎ、日々の風景を彩り、家族の思い出を刻む場所。朝・昼・晩、いつ訪れても高知らしい風景が、喫茶店にある。
(※)総務省統計局や全日本コーヒー協会が過去に行った調査によるもの。
アサ喫茶
海を見ながらモーニング
通い続けたい朝のひと時が喫茶店にある

喫茶アロエ(P07掲載)の常連 黒岩 喜佐子 (くろいわ きさこ)さん
黒岩さんご夫妻が「喫茶 アロエ」でモーニングを食べるのは、15年間変わらない毎朝の習慣。以前はマグロ漁師だったというご主人の敬典(けいすけ)さんが転職したことをきっかけに、夫婦でモーニングに通うように。
今では、子どもや孫と一緒に訪れることもあれば、誘った友人と連れ立ってやってくる日も週に何度かあるそう。喜佐子さんは「海を見ながらモーニングを食べる、この朝のひと時がたまらなく好きながよ。元気でいられるうちは通い続けたい」と微笑む。
ヒル喫茶
喫茶は変わらない日常
僕の暮らしは変わっても この店は変わらない

エヴァンス(P09掲載)の常連 たっちゃん さん
まんが好きのたっちゃんは、店主の古くからの友人。定年で仕事を離れた今でも、週に一度は「エヴァンス」を訪れ、晩ごはんを兼ねた遅めのランチを楽しむ。勤め人だった頃は、仕事終わりに毎日のように訪れては、コーヒーを片手にまんがを読みふけった。そんな風に一人で過ごすこともあれば、仲間内で集まる場所としてもよく利用するのだとか。「ライフスタイルが変わっても、ここに来るのは日常やね」と話してくれた。
バン喫茶
一日を締めくくるひと時
オンとオフが切り替わる場所

ジャズ喫茶 木馬(P14掲載)の常連 高橋 一世(たかはし かずよ)さん
「夜、音楽と本に囲まれたこの喫茶店で、お酒を嗜みながら過ごす時間が好き」と話す高橋さん。ジャズ喫茶「木馬」とは、25年前にライブを聴きに行って以来の付き合い。今では仕事が終わった後に訪れるのが日課となっている。お酒を味わいながら音楽を楽しんだり、本を読んだり、マスターや他のお客さんと会話を交わしたり。高橋さんにとってそのひと時は、一日を終えた自分へのご褒美であり、同時に公私を切り替えてくれる大切な時間でもある。