
高知の郷土料理「皿鉢」は、お正月や婚礼、祝い事には必ずと言っていいほど登場する。
いったい、皿鉢料理とは……。

皿鉢大解剖
【歴史】
古くは江戸時代、武士の本膳料理に彩りを添えるため、大皿に盛った料理を出したことが始まりと言われている。 明治になり、豪商や富農が競って大皿を買い求め、宴席に並べる現在の〝おきゃくスタイル〟になっていったようだ。
【 形 】
生(刺身)と組み物(盛り合わせ)が基本のセット。別に、カツオのたたきや、たいそうめん、蒸しだい、ぜんざいなど、お客の人数を見て皿を足していく。
高さ──通常、真ん中を高く盛る。祝い事は高さを増し、法事では低く盛り付けた。高さのある生け作りは圧巻。
数───めでたい時は奇数の料理を盛り付けるという地域が多い。ただし、幡多地域では祝い事に偶数を使う地域もあった。
【料理】
老若男女問わず同じテーブルで楽しめるようにさまざまな料理が盛り込まれるが、皿鉢を構成するいくつかの要素がある。
魚───新鮮な魚が豊富に揚がる高知の宴会には、生の魚が欠かせない。皿鉢には、旬の魚介類の刺身、カツオのたたき。ブリの刺身は葉ニンニクの効いた酢みそ「ぬた」が用意されることが多い。法事では、生魚の代わりに厚揚げ豆腐を代用する地域もあった。
すし──米が貴重とされていた江戸時代から、高知のハレの日のごちそうと言えば、おすし。海岸部では獲れたての魚を、山間部は塩蔵したサバを使う〈姿ずし〉。のり、昆布、卵、大菜などで巻いた〈巻きずし〉も定番。ミョウガ、リュウキュウ、チャーテ、シイタケなどの〈野菜や山菜のすし〉も人気がある。
練り物──水揚げの多い港町では、さまざまな練り物が開発された。すり身に高野豆腐やシイタケを付けた「づけ」や、ゆで卵がまるごと入った「大丸」は高知ならでは。
和え物・煮物・揚げ物・焼き物──季節の料理がたくさん盛り込まれる。焼いた貝類、アユの甘露煮、白和え、酢味噌和え、昆布巻き。子どもにはエビフライや唐揚げが人気。
甘味──羊羹は必須で、夏は水羊羹、冬は蒸し羊羹、三色羊羹は年中ある。他にも、きんとんや季節の果物などを二品以上盛る。
【言葉】
「皿鉢」と「おきゃく」は、切っても切れない関係。皿鉢やおきゃくから生まれた独特の言葉がある。
皿鉢──さーち、さあち、さわち、さはち……呼び方は人それぞれ。大皿そのもの、また大皿と料理を総称しても使われる。
おきゃく──宴席のこと。かつては冠婚葬祭や神祭の酒宴のことを指したが、現在では幅広く使われる。
その他の言葉──調理場では、余るほど作らないと足りないと言う意味で〈あまらなたらん〉。過不足なくちょうどですむと「ぼっちり」と言って胸をなでおろした。また、宴席にいつまでも残って飲み続けて帰らない客のことを、皿鉢に残ったハランになぞらえ〈ハラン組〉。おきゃくの後や翌日に、残った皿鉢に新しい料理を足してする内輪の慰労会のことを〈残(ざん)をする〉と言う。次の日に残ったサバずしを炙って食べると絶品。
皿鉢を追って
皿鉢料理は土佐名物と言うけど、「単なる盛り合わせだろ?」「オードブルはどの県にもあるんじゃない?」「おせちとどう違うの?」と言った囁きが聞こえてくる。 そんな謎を追って、各地を訪ねた。
進化する皿鉢
 正月のおせち料理に「皿鉢」を食べようとなると、最近はほとんど仕出し屋に注文する。
正月のおせち料理に「皿鉢」を食べようとなると、最近はほとんど仕出し屋に注文する。
大晦日だけで500皿以上注文を受けるという本池澤は、大正14年に魚屋として創業し、昭和31年から仕出しを始めるようになった。昭和30年代以降、皿鉢のつくり手が家庭から仕出し屋に移ってきた。
料理長の杉本長寿さん(54)は「これだと、家族みんなで楽しめるし、急に人が来ても平気。おきゃく文化の高知にはもってこいの料理」と言う。昔ながらの料理を守りつつ、刺身とすしを一緒に盛ったり、唐揚げやエビフライを載せたり、フルーツだけの盛り合わせをしたり、皿鉢はお客さんの要望に応えて進化してきた。
❖とさぶし編集委員の一人が「おきゃくの達人がいるよ」と教えてくれた。県西部の「お町」、土佐の小京都と言われ独特の文化を持つ四万十市に向かった。
毎日おきゃく
一條大祭でにぎわう四万十市の中心街から北へ車で数分、若藤地区の宮川昭雄さん(64)を訪ねた。
おきゃくの会場は自宅の隣にある自作のログハウス。中央のテーブルには手作りの大皿。カマスの姿ずし、黒こぶの巻きずし、揚げ物、サラダが盛られ、隣の皿は刺身とカツオのたたき。
“プシュッ”。「先に練習やろうか」と缶ビールをあける。「冷(ひ)よう(※)なったねえ」と近所の人がやって来るたびに食べ物や酒が増えていき、“練習”が繰り返される。全員が揃ったところで乾杯。「酔わん酒は飲まん。頭がしびれるばあ(※)やないと」。杯を注しあい、一升瓶がどんどん空いていく。よく聞けば、これが毎日のようにあると言うので驚きだ。
「ここは一条氏に仕えた地。公家の文化やけん(※)」と宮川さんが豪語する。一条氏といえば、順序や盛り付けのルールの細かい本膳料理や懐石料理の文化なのでは……と疑問が浮かんだが、ここも土佐の文化と納得した。
❖創刊号制作時に訪れた室戸市高岡地区の神祭。そこで聞いた室戸ならではの皿鉢を思い出した。
見栄っぱりの皿鉢
“ごくどうされ”(※)──「めんどくさいから皿に盛っておけ、という意味よね。いつもは刺身で酒を飲むけど、神祭と正月は皿鉢で酒を飲む」。祖父から三代続く漁師の山下幹雄さん(52)は、かつての皿鉢の風景を思い出す。
室戸岬の東側は、栄養分豊富な深層からの海流が湧きあがり、アジ、サバ、ブリなどいろんな魚が集まってきて、かつてはマグロやクジラも現れた。室戸では、江戸時代に始まった近海クジラ漁が明治期に南氷洋へと広がり、昭和期はその技術を遠洋マグロ漁に用いて発展した。
結婚式、家の建て替え、さらに不漁や事故の後でも“験(げん)を立て直す”と、何かにつけて酒を飲んだ。「バブルの頃は見栄の張り合い。次から次へと皿鉢を出すし、盛る高さがだんだん高うなってきた」。酒を切らして主人に恥をかかせないよう妻が目を配り、お手伝いもいっぱいいた。「翌日はお手伝いさんを接待して、翌々日は自分らの慰労をして、三日三晩飲み明かしたもんよ」。室戸の人の派手好きで豪快な気質は今も健在だ。
❖グリーンツーリズムの調査をしている人からの情報で、愛媛県との県境・津野町(旧東津野村)へ、茶畑の広がる峠に車を走らせた。
家々の味

宮谷集落は、かつて製紙原料の栽培で栄えた地。
「秋の神祭は、案内を受けていようとなかろうと家々を回る。無礼講で、時には駐在さんまで来た」。川田信喜さん(85)にとって、この日は特別な日。深夜2時頃から皿鉢の支度をした。「魚を酢につけてすしをやり、山芋のとろろをしたり、川魚の煮つけをしてみたり」。直径約40㎝の皿鉢に、山盛りのウナギのかば焼きを作ることもあった。骨を焼いて漬けこんだ秘伝のたれが自慢。噂は高知市内まで広まり、料亭の旦那が「川田さんのかば焼きにはかなわん」と言うほど名人だったという。
高知県全域に仕出し屋ができる前、神祭や冠婚葬祭の食事は各家々が用意するのが普通だった。〝器用やり〟と呼ばれる男性の、しかも素人の料理人がハレの日の料理を担っていた。
子どもたちが「あこのすしはおいしい」と噂するほど評判の家もあり、〝器用やり〟自身が各家を回って舌を肥やし、調理法を研究して腕をあげたという。
「おきゃくが盛り上がってきたら、皿鉢の縁を箸で叩いて、唄をうとうたもんよ」。賑やかだったおきゃくの話は尽きない。
❖同じ町内(旧葉山村)に皿鉢をつくる女性グループがあると聞き、訪ねた。

担い手は女性へ
 先人が石を積み上げ作っただろう、狭い水田が残る久保川地区。女性グループ代表の笹岡三栄さん(75)は、毎年お正月に皿鉢を作る。「めでたい時は奇数。だいたい11品」。ハランも自分で切る。「上手な人は『寿』の字を切り込んだりしよった。5月に作るときは、菖蒲の形をやるがよね」。皿鉢料理に欠かせないハランは、今も自宅で皿鉢をする家の庭先に必ず植えられている。
先人が石を積み上げ作っただろう、狭い水田が残る久保川地区。女性グループ代表の笹岡三栄さん(75)は、毎年お正月に皿鉢を作る。「めでたい時は奇数。だいたい11品」。ハランも自分で切る。「上手な人は『寿』の字を切り込んだりしよった。5月に作るときは、菖蒲の形をやるがよね」。皿鉢料理に欠かせないハランは、今も自宅で皿鉢をする家の庭先に必ず植えられている。
「よそに冠婚葬祭があるいうたら、父が前掛けに包丁二本くるんで、ハランを取って行った。私はぎっちり付いて、てごをしよったきね。それでひとりでに覚えた」。ハハハと笑い声をあげる。「昭和40年代までは、この50戸の集落に5、6人の男の料理人がおったけど、いつの間にか、料理をするがはみんな女に代わってしもうた」。
笹岡さんは「季節の花を飾ったらうんとえい」と言う。グループの女性と考案した菊ずしは、赤、黄、緑の色が美しい。がんこな器用やりの精神を受け継ぎつつ、はちきんのもてなしの心が皿鉢に融合している。
❖知り合いからおもしろそうな情報を得た。大学生だけで皿鉢をするという。
未来の皿鉢

ここはひろめ市場。大学生が10人ほど集まり、アオサの天ぷら、どろめ、土佐巻……どんどん皿鉢に盛っていく。通りがかった客が足を止め、「それえいねえ!」「まっこと、おきゃくやねえ」と声をかける。
川村聡志さん(23)は、いつもと違う飲み会をしたいと思いついて、家にあった大皿を持ち込んだ。一人5000円ずつ出し合い、余ったお金は東北に寄付すると決めた。「お腹いっぱいになるし、楽しいし、テンションもあがる↑↑」。県外から来ていた学生も大喜び。味をしめたのか、2回目も開催した。
若者から年配者までが集うフードコート「ひろめ市場」、鳴子とよさこい節の他は衣装も踊りも思いのままの「よさこい祭り」。これら高知で生まれた名物と、大皿に載せたいものを載せて進化を続ける「皿鉢料理」はどこか共通している。いずれも土佐人の自由さと遊び心から育った、とするのは言いすぎだろうか。
![]()
※冷やい=寒い ※ばぁ=〜くらい ※〜やけん=〜だから。幡多地方では「〜やき」ではなく「〜やけん」を使う。幡多はイントネーションがやさしく癒し系。
※ごくどう=ずぼらな、まめでない人 ※あこ=あそこ、の意味。場所を差す言葉 ※ぎっちり=一生懸命、根つめて ※てご=手伝い/うんとえい=とても良い
※はちきん=快活な女性のこと。頑固な男性はいごっそうという ※まっこと=本当に、まさしく。強調する言葉
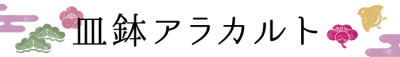
 【土佐町】川の町の皿鉢
【土佐町】川の町の皿鉢
吉野川が流れる嶺北地域では、イタドリやゼンマイやウドなどの山の幸、ウナギやアユやテナガエビなどの川の幸が盛りだくさん。地元で採れる米も海岸部から運ばれてくる魚も貴重だった頃から、特にサバずしはおいしいと評判になるほど、調理の工夫が重ねられてきた。 料理:サバずし、ウド酢味噌和え、ゼンマイ煮物、イタドリ煮物、リュウキュウ酢の物、シシ肉煮など(写真:すえひろ屋提供)
 【室戸市】豪快な皿鉢
【室戸市】豪快な皿鉢
室戸はクジラ漁、マグロ漁の基地だったこともあり、この2種は必ず入れる。マグロの腸や卵の煮つけは美味だが、かつての日常食だったためエビやメロンがないと物寂しい気がするという。時に高さ競争が起きて、直径約50cmの皿鉢におすしが30cm以上の高さに盛り付けられることもあったとか。 料理:流れ子煮、クジラ竜田揚げ、マンボウの腸の味付け、マグロの腸・卵の煮つけ、イカとフグの天ぷらなど (料理:ぢばうま八)
 【黒潮町】漁師町の皿鉢
【黒潮町】漁師町の皿鉢
カツオ近海一本釣り漁獲高日本一の船が出るほどの土佐佐賀。カツオの刺身やたたきは漁師自ら包丁を握る。姿ずしはサバではなくアジやカマスを使うことが多く、昆布の巻きずしも欠かせない。酢飯はゴマと刻みショウガの他に、魚の身をほぐした「そぼろ」を必ず入れる。 料理:カマスの姿ずし、巻きずし(海苔、黒こぶ、卵)、流れ子煮、うなぎ入り卵焼き、ニッキ羊羹など(写真:藤本商店提供)
 【津野町】菊ずし
【津野町】菊ずし
これも現代の皿鉢料理。大皿に載せたいところだが、すしの色が引き立つ器に入れられる。シソで赤色を付けた大根、深い緑の大菜、黄色い卵の3色で菊の花を表現。すしに欠かせないガリは、バラの花に見立てている。メインではないが、テーブルが華やぐ一皿となる。(料理:久保川生活改善グループ)
 【南国市】組み物の原形
【南国市】組み物の原形
香長平野が広がり農業が盛んな南国市。かつて富農が多く、競うように武士が持っていた皿鉢を購入したという皿鉢料理誕生のルーツのような場所。昭和初期、各家々で皿鉢料理を作っていた時代の"組み物"を再現するとこうなる。 料理:サバずし、巻ずし(海苔、白昆布)、稲荷ずし、昆布巻き、酢ごぼう、高野づけ、柿、きんとん、羊羹 (出典:松崎淳子さん「高知はこんなところです」)
 蒸しだい
蒸しだい
めでたい時は、蒸しだい。背開きした鯛におからをどっさり詰めて蒸しあげる。葉ニンニクと甘口のおからが、なんとも言えないハーモニーを醸し出す。(料理:南国市農漁村女性グループ研究会)
 【大月町】柏島の皿鉢
【大月町】柏島の皿鉢
豊後水道に面した海岸は、小さな入り江がいくつもあり、様々な魚が揚がる。柏島の皿鉢は、地元の人が大好きというアジやブリの魚の姿ずしは必須で、皿の前、中、後ろに3本置かれる。もう一つ必須なのが、魚のすり身と高野豆腐を煮付けた「高野づけ」。さらに、ゴボウなどの野菜や海岸で採れるフノリを揚げた「つき揚げ」など、島特有の料理が15品盛られる。(写真:お好み きみ提供)
 【安芸市】入河内の皿鉢
【安芸市】入河内の皿鉢
県内最古の皿鉢の記録「森家の日記」(1799年)が残る安芸市。大根で有名な山間部の入河内地区は、夏と秋の神祭に、婦人会やJA女性部が皿鉢を作る。メインのすしは、ゴマとショウガの他に刻んだちりめんじゃこを混ぜるのが入河内流。他にイタドリやワラビ、かき揚げや果物を並べる。昭和50年頃まで作っていた、樫の実でつくる「かしきり豆腐」は、食感を楽しむ料理。「ぬた」をかけて食べ、酒の肴にもなっていた。 (写真:安芸市役所 小松幸司さん提供





